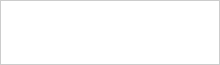私は、日本共産党を代表し、市政の諸課題について順次質問いたします。
 2024年度一般会計決算は、歳入約1兆2,401億8,800万円にたいし、歳出約1兆2,303億円と、最終予算額にたいする歳出の執行率は92.5%となりました。
2024年度一般会計決算は、歳入約1兆2,401億8,800万円にたいし、歳出約1兆2,303億円と、最終予算額にたいする歳出の執行率は92.5%となりました。
事業が年度内に完了できなかった等の理由から、翌年度に繰り越すべき56億7,000万円を差し引いた、残りの剰余金42億1,800万円のうち基金条例に基づき22億円を財政調整基金に積み立て、約20億円については翌年度に繰り越しました。
その結果、財政調整基金は、政令市移行後2番目に多い59億円を支障したとされながら、年度末残高は283億円となりました。これは札幌市が維持するとしている100億円を大きく上回る規模といえます。
2024年度の物価高騰対策は、低所得者や幅広い市民向けの支援策が必要でしたが、国の財源は活用されたものの、一般財源を活用した札幌市の独自策は打たれませんでした。
物価高騰対策の原資として活用する余地が、残されていたと指摘させていただきます。
はじめに、市長の政治姿勢です。
質問の第一は、多文化共生社会と排外主義についてです。
7月の参議院選挙結果は、衆議院と同様に与党が過半数割れとなり、9月7日、石破首相が辞任を表明しました。この選挙結果は、裏金問題への無反省や、物価高騰に対する手立てのなさ、アメリカ言いなりの大軍拡などの状況に、国民が厳しい審判を下したことの現れであり、我が党は、総裁選の最中であっても、早急に臨時国会を開催し、多くの課題に応えるべきだと考えます。
この参議院選挙では、物価高騰など国民生活の苦難に対し、現金給付か消費税減税かが大きな争点でしたが、一方で、SNSなどネット上を中心に、外国人や様々な民族を公然と敵視し差別をあおる排外主義が広がりました。
質問の1点目は、外国人に関する事実の歪曲とその宣伝・拡散行為についてです。
参議院選挙中、例えば、「外国人は生活保護を受けやすい」、「外国人は来日初日から日本の国民健康保険が適用される」などの誤った情報が、インターネットやSNSで200万回以上表示されました。
厚生労働省の「被保護者調査」によると、外国籍を持つ生活保護利用世帯が全体に占める割合は2.87%程度です。永住者や定住者など国内での活動制限がない在留資格を持つ人に限って受給資格が得られるため、「生活保護を受けやすい」状況ではありません。国民健康保険も、90日以内の短期滞在ビザの外国人は住民登録ができないため、公的医療保険に加入できません。
しかし、参院選前の6月、NHKが行った世論調査では、「外国人は優遇されていると思う」と答えた人が64.0%となり、誤った情報をもとに回答した人が多かった可能性が現れる結果となりました。また、選挙中には、「違法外国人ゼロ」、「外国人比率の上昇抑制」、「外国人土地取得規制法の成立めざす」など、外国人が優遇されていることを前提にした政党の公約が追加されました。
こうしたことを反映し、7月24日、全国知事会では「青森宣言」を出し、「排他主義、排外主義を否定し、多文化共生社会を目指す我々47人が」、「民主政治を脅かす不確かで根拠のない情報から国民を守り」と、正しい情報に基づいた政治参画を求め、宣言を行いました。
「外国人は優遇されている」などの歪んだ情報は偏見や差別を助長するものですが、こうした情報を故意にインターネットや街頭で拡散しようとする動きについて、市長はどのように対処されるのか、うかがいます。
質問の2点目は、様々な民族の存在の否定と多文化共生社会についてです。
札幌では、9月に地下歩行空間で「アイヌの史実を学ぼう」という、民族排除を表現するパネル展が実施されたところです。アイヌ民族がもういないかのように扱ったり、優遇されているかのように喧伝する内容のものです。アイヌとしての言語や慣習など民族らしい暮らしが奪われた上に、さらにその存在をも否定しようとする動きは、看過できません。
特定の民族の優遇を強調することは、他の民族を排除しようとすることであり、札幌市が目指す「多文化共生」の社会とは逆行し、人権侵害、ひいては民主主義そのものを脅かすものだと考えますが、このパネル展について、市長の見解と対処方針についてうかがいます。
質問の第二は、泊原発とGX特区についてです。
その1点目は、泊原発3号機の再稼働への動きについてです。
今年7月30日、原子力規制委員会が泊原発3号機を「新規制基準に適合している」とする審査書案を了承しました。北海道電力は、2027年にも泊原発3号機を再稼働させようと動き始めています。北海道の鈴木知事は記者会見で、「道民や関係自治体も含めたさまざまな声を総合的に判断したい」と答えており、今月20日からは住民説明会が始まっています。
札幌市は、泊原発から約40㎞~80㎞に位置するため、原子力災害から免れることはできません。また、近年の異常気象は想定を超える規模となっており、地震もまた、想定の範囲とは限りません。
市長は、原発の再稼働についての我が党の質問に対し、情報提供と説明責任、安全の確保が必要だと答弁されてきましたが、このたびの泊原発3号機の審査結果は、原発の安全が確保できているとお考えなのか、うかがいます。また、鈴木北海道知事に対し、どのように働きかけをおこなうお考えか、うかがいます。
質問の2点目は、GX特区によるESG債の使途についてです。
9月10日、札幌証券取引所は、環境・社会・企業統治への貢献に限った機関投資家向けの債券市場「北海道ESGプロボンドマーケット」を開設し、北海道電力は、ESG評価を取得した10年債・120億円、20年債・25億円の2銘柄の承認を受けました。
この債券市場により2030年度のCO2排出削減目標の達成、および2050年カーボンニュートラルの実現に向けた資金調達基盤が確立されるとしていますが、その資金の使途には原子力発電の再稼働が含まれています。
市長は、繰り返し可能な限り原発への依存度を低減していくと答弁され、積極的に「GX特区」となってからも、省エネ推進や再生可能エネルギーを拡大することで、依存度を低減すると説明されてきました。
「ESG債」の使途として、原発再稼働のための資金が使われることへの市長の見解とともに、原発再稼働への資金投入が、原発への依存度を高めることにつながると考えますが市長の認識を伺います。
次は、市民の暮らしと市民負担増についてです。
質問の第1は、物価高騰における、札幌市経済への影響についてです。
物価高騰は、急激な円安による外的要因から、現在は、原材料の高騰に加え、光熱費の上昇による生産コストの増、人手不足による労務費や物流費の上昇など、複合的に重なった内的要因により、継続的な価格引き上げが起こっています。
帝国データバンクの調査では、9月から、家庭用を中心とした飲食料品の値上げは1,422品目にのぼり、2022年に統計を始めて以来、単月の値上げ品目数としては4ヶ月連続で1千品目を超えています。
物価上昇を背景に、家計に占める、名目個人消費は増加していますが、実質個人消費は、コロナ感染拡大後の落ち込みから少し回復したあと、物価上昇とともに伸び悩んでおり、購買力が低下していることがわかります。
この実質個人消費の動向は、基本的には、家計が自由に使える所得のうち、消費に使える金額である実質可処分所得の動向を示したものと考えられます。
国内総生産GDPの約55~60%は、個人消費です。リーマンショックや新型コロナで個人消費が落ち込んだ時、経済全体がマイナス成長となりました。つまり、国民の消費が経済のエンジンであり、持続性のある物価高騰対策には、実質賃金の増加が重要です。
札幌市の事業所数は7万5千件を超えると言われています。従業者99人以下の中小企業・小規模零細企業が98%を占めており、そこで約70%の市民が働いていますが、企業も物価高騰のあおりを受けて賃上げが進まない状況があります。
また、家計の世帯構造をみるとき、勤労者世帯、年金のみで暮らす無職世帯や自営業世帯があり、賃上げがあったとしても、その恩恵が届きにくい世帯の割合も少なくありません。
物価高によって、どの世帯も家計は支出を抑制せざるを得ない状況が、札幌市経済にどのような影響を及ぼしているのかお聞きします。
質問の第2は、自治体の役割と、来年度から実施予定の市民負担増に係る計画の見直しについてです。
札幌市は、他の政令市より市民所得が低く、税金の支出、燃油を含む水光熱費などのライフラインや生活費の支出は、ここ数年重みを増し、生活の困難をより深刻にしています。
そのような中、札幌市は、苦しい市民の生活に追い打ちをかけるよう、これまでのサービスに市民負担を導入、増額、あるいはサービスを後退させる計画の実施を行おうとしています。
1点目は、敬老パス制度の継続と検証についてです。
札幌市は、「敬老優待乗車証(敬老パス)の制度を変えて、みなさんに福祉が届くようにする」とのべ、対象年齢と自己負担割合を引き上げ、利用上限の減額を行う新制度へと変更を決めました。
2023年度、札幌市が行った実態調査アンケートでは「敬老パスがあるおかげで、楽しみや生きがいを得ることができる」「健康のためにも、大変便利に使っている」、このような回答が多く寄せられました。これら喜ばれている事業を継続、または充実することこそ、自治体が市民に行うべき施策ではないかと考えますが、いかがか伺います。
札幌市は、敬老パス制度の今後について、「2026年度から見直しを行い、5年後を目途に健康アプリと併せた事業費負担等を検証し、敬老パス制度について必要に応じて所要の措置を講じる」としています。敬老パス事業を縮小しながら、健康アプリと併せて、検証を行うというものですから、利用状況や効果、事業費などに格差が生じます。現行制度によって検証を行うことが公平であり、検証期間のスタートとなる来年度は、計画している敬老パスの見直しを中止すべきと思いますがいかがか伺います。
2点目は、火葬料金有料化による市民負担等についてです。
2025年第1回定例会で、「札幌市火葬場条例の一部を改正する条例案」が可決され、現在無料である市民の火葬料を、来年度から16,000円などに有料化することが決まりました。
現在、人間関係の希薄化や厳しい経済状況、宗教概念の変化などから家族葬が増え、通夜や告別式を行わず火葬のみで見送る直葬も増えています。
札幌市は「有料化に際し、市民にとって過度な負担とならないよう、火葬場を運営するために係る費用の概ね50%を市民に負担いただく」と説明しました。物価高騰で、なお生活が苦しい中、さらに火葬料金が有料化されることは、市民にとって過度な負担であると思いますが、どのようにお考えか伺います。
札幌市は「火葬場は市民生活に欠かせない施設であり、公衆衛生の確保などの観点からも、公益性の高い施設である」と認識を示しながら、火葬という行政サービスを受益として、市民に負担を求めることは、住民福祉の増進を図る、地方自治の本旨に逆行すると考えますがいかがか伺います。
3点目は、市営住宅の管理戸数の見直しと公平性、自治体の公的役割についてです。
建設委員会で報告された「市営住宅家賃制度及び減免制度の見直し(案)」は議会議決は必要なく、市長の決裁で施行できると聞いております。
地下鉄近郊やエレベーターがある、省エネ機能が高いZEHなど、団地の立地や設備水準から得られる利便性は、住宅によって違いがあります。札幌市は家賃見直しの必要性を、「利便性を家賃に反映し、入居者間の公平性を確保するもの」と述べています。
あわせて札幌市は、市営住宅の家賃収入が減少している理由として、建物の経過年数によって家賃が毎年下がっていくことに加え、建替えや借上市営住宅の返還に伴い管理戸数が減少していることをあげています。それならば、倍率が高くて応募しても入れない市営住宅から、入りやすい市営住宅へ、管理戸数を増やす計画にしてはいかがかと思いますが、お考えを伺います。
市営住宅についてパンフレットでは、「住宅の確保に困っている所得の少ない方々に対して、札幌市が提供している住宅」であると、明記されています。
入居者の公平性を言いますが、市営住宅の役割からして、便利なところを値上げするのではなく、不便なところをもっと下げていくことで公平性を確保すべきと思いますが、そのようなお考えはないのか伺います。
来年度からの見直しで、入居者の30%以上の世帯に引上げの影響が出ます。これにより札幌市への家賃収入は、7,900万円増にもなるという見込みですが、これは、低所得の入居者に家賃負担を増やし、札幌市の市税支出を減らすということです。経済的な負担能力に応じて税負担をする応能負担から、利便性を理由に応益負担を強いることは、地域における行政を自主的、総合的に実施するという自治体の公的役割について問われる問題だと思いますがいかがか伺います。
4点目は、市民負担増の認識と見直しの市長の決断についてです。
すでに市有施設の利用料・手数料が値上げされ、下水道料金の値上げも検討されています。市民の暮らしの大変さは待ったなしの状況であり、暮らしへの支援は、将来に先送りできるものではありません。
市民負担増は、いまでさえ苦しい暮らしを厳しくし、さらに市民の購買力を奪うことになると思いますが、認識を伺います。
敬老パス、火葬料金有料化、市営住宅家賃見直しなどは、札幌市独自で行ってきた、市民に喜ばれている制度を削るものであり、認められません。
来年度実施予定の市民負担増は、やめるべきであり、市長の決断を求めますが、お考えを伺います。
次に、まちづくりについてです。
秋元市長は就任した年の市議会で「民間投資を呼び込む再開発事業は未来への投資」と説明し、その立場は10年間変わることなく、都心の再開発やGX投資などに貫かれてきました。
アクセス道路や北海道新幹線札幌延伸など、それら総事業費は増大し、事業の規模や期間を見直さない限り、さらなる市税投入が避けられない事態になっています。
一方市民は、当時の冬季五輪招致について「オリンピックよりも市民の施策を優先してほしい」と要望し、市民理解を得られないまま、五輪招致は断念することとなりました。当時と同様、市民は、新幹線延伸より地元のバス路線の充実、除排雪の拡充を望み、民間に補助金を出すタワーマンションや高級ホテルの建設より、暮らしに必要な保育や介護などの公的施設の建設を求める声が広がっています。
2024年度決算では、北5西1.西2地区、北4西3地区、大通西4南地区の民間再開発促進費、いわゆる補助金に52億7,900万円が費やされ、大企業などが手掛ける民間再開発の補助金として、2024年度までに225億4,700万円が投入されています。
「大企業が稼げるまち」に貢献し、投資を呼び込む事業を優先してきた市政を、暮らしや福祉、地域密着型の公共事業を優先するまちづくりに転換すべきです。
質問の第1は、開発優先のまちづくりについてです。
1点目は、新MICE施設整備基本方針についてです。
9月に公表された中島公園隣接地への新MICE施設整備基本方針は、2018年当初の事業費280億円から2倍以上ともなる592億円という内容です。
今定例会に提出された、令和7年度一般会計補正予算案に、新MICE施設整備基本方針に基づき、2028年・令和10年度に整備予定地を購入するため、土地売買契約を締結する予算として「新MICE施設整備予定用地取得費」が債務負担行為として計上されています。
「取得にかかわる予約契約に基づいて算定する不動産鑑定評価額」と説明がありますが、整備方針では昨年10月時点で約105億円という高額な鑑定額であるにもかかわらず、補正予算であるのに金額が示されていません。2028年度に土地を購入し取得することの議会承認を求めるものですが、将来、購入時の土地の価格については白紙委任するものであり、到底認めることはできません。
事業計画のスケジュール予定では、基本計画案を示した後、2026年度にパブリックコメントをおこなうこととなっております。市民から寄せられた意見を考慮して計画の是非を検討するはずですが、市民の意見を聞く前に、事実上土地の購入を決めることは、パブリックコメントを形骸化させることに等しく、市民不在そのものです。
これらは、市民の理解と納得を得られるものではないと思いますが、いかがか伺います。
2点目は、都心アクセス道路の地元負担と需要や効果についてです。
都心アクセス道路の総事業費は1,200億円であり、札幌市負担は240億円であると、市民は説明を受けてきました。
しかし、地下構造のために下水道管移設におよそ330億円、水道管移設に34億円ほどの費用がかかる予定です。
国の負担や補助金を入れてもなお、これらの移設に係る札幌市の負担は165億円程度となる見込みです。
昨今の物価や人件費の上昇の影響から、地元負担が増加する懸念はぬぐえませんが、札幌市のお考えを伺います。
都心アクセス道路は、需要やその効果を検証しないまま進んでいますが、札幌市としての検証を行う考えはないのか伺います。
質問の第2は、住民のためのまちづくりについてです。
1点目は、市民置き去りのまちづくりについてです。
自治体の役割としての、住民の福祉の増進という視点でみると、再開発が進む一方で、まち全体の公的施設の後退が目立ちます。
市立保育所は、子育て支援センター・ちあふるの整備に伴い廃止する方針をすすめてきました。ちあふるが全区に整備されたにもかかわらず、施設の老朽化を主な理由として、現在17園しかない市立保育所のうち、東区と白石区で4園もの廃止方向を示しました。
また、様々な困難を抱える母子家庭の支援施設、札幌市しらぎく荘も老朽化で、改築を検討せず廃止されました。
高齢者の住まいの確保の困難さと、家賃補助の必要性を認識しながらも、国土交通省が高齢者優良賃貸住宅の家賃補助期間について、20年の延長を示し自治体で勘案するよう通知しているにもかかわらず、札幌市が延長をしないと判断した姿勢は、住宅セーフティネット施策を後退させるものです。
月寒体育館は、市民の利便性を優先するならば現在の場所に建て直すことが優位ですが、五輪招致のための計画を引き継ぎ、レバンガの拠点となる方向が失われてからも、大和ハウスプレミストドームに隣接する案に固執しています。
このように、市民が日々の生活で活用し、必要としている施設について、老朽化や開発を理由に縮小、廃止をすることは、利用している住民を始めとする市民を置き去りにしたまちづくりであると考えますが、どのような認識か伺います。また、市民の意見を充分に取り入れた計画にするべきですが、お考えを伺います。
2点目は、優先すべき事業についてです。
市立札幌病院は建物が老朽化しており、またコロナ禍で経験した新たな感染症の対応や、高度医療の機能強化のため、再整備計画がすすんできましたが、必要でありながら、経営改善を理由に半ばでストップしています。札幌市衛生研究所では高度な検査機器の更新の遅れや、設備の老朽化による影響も出ており、課題となっています。
橋梁、下水道の老朽化、耐震化などの整備は築40年を超えても、修繕をしながら80年、100年の長寿命化を図り財政的な負担を平準化する方針です。道路の修繕やバリアフリー化も平準化を考慮していますが、インフラには市民生活の安全が担保される整備が必要です。
これら市有施設やインフラ整備は、市民の命とくらしに直接かかわる待ったなしの課題であり、事業のなかでも優先すべきですが、市長のお考えを伺います。
次は、中小企業支援についてです。
賃金の引きあげは、人手不足解消のうえでも有効ですが、資本力がない中小事業者にとっては、経費増が伴うことから実施に踏み切れないとの声を聞きます。
国の中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金をみても、事業所内で最も低い賃金を30円以上引き上げ、生産性に資する設備投資などを行った場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を支援する制度であり、賃上げのみを実施したい事業者は対象にはなりません。
融資制度においても、ゼロゼロ融資の借換え資金とされてきた伴奏型経営改善資金が2024年6月に終了し、札幌市は既存の小口融資の活用も呼びかけていますが、返済の不安から新たな借り入れに踏み切れない事業者も多く、事業者の資金需要に応えた実効性のある支援策が待たれています。
中小企業支援において中小事業者が待ち望んでいるのは、給付や助成金による賃上げ支援、実質的な直接支援にもなる金利を据え置いたうえでの返済期限の延長、利子補給などですが、札幌市においても実施に踏み切るべきと考えますが市長の見解を伺います。
次は、気候危機と暑さ対策についてです。
昨年、温室効果ガスの年間排出量が過去最高を記録する中で、国連環境計画UNEP(ユネップ)は、パリ協定で設定された、気温上昇を1.5℃に抑える目標と、2℃を大幅に下回る数値に抑える目標、いずれも厳しい状況だと述べ「気温の破滅的な上昇を防ぎ気候変動による最悪の影響を回避するために、緊急行動を起こさなければならない」と報告しています。
2025年11月の地球変動枠組み条約COP30の開催を目前に、国はもちろん自治体の気候変動対策の責任が大きく問われています。
質問の第1は、札幌市気候変動対策行動計画についてです。
札幌市もパリ協定での目標を踏まえ、気温上昇を1.5℃に抑えるため、2050年の目標を、温室効果ガスを実質ゼロとする「ゼロカーボン」を掲げ「省エネルギー対策」「再生可能エネルギーの導入拡大」「環境負荷の少ない自動車の普及」「資源循環」など気候変動対策に取組み、2030年の目標を2016年比で55%削減する計画としています。
しかし、札幌市においても想定を超えた、気温上昇や北海道で初めて線状降水帯による豪雨が起きていることから、計画の見直し検討も視野に入れることが必要と考えます。
2030年までに約5年の期間を残すばかりとなりました。札幌市気候変動対策行動計画のCO2削減の実績と課題について伺います。また、計画見直しの必要性はないのか、お考えを伺います。
質問の第2は、猛暑に対応した市民生活への支援についてです。
1点目は、エネルギー貧困への認識と札幌市の役割についてです。
世界では、世帯収入に占めるエネルギー比率が10%を超える家庭を「エネルギー貧困」とし、社会課題として認識されています。
札幌市においても「冬期間の灯油代が家計を圧迫し、ストーブをつけるのは3時間のみ。お客さんが来た時以外はストーブをつけない」「エアコン購入の資金を用意できず、じっと暑さに耐えている」などの実態が届いています。光熱費の高騰が続けば、さらに深刻さが増し、命にもかかわる懸念が広がります。
札幌市は、気候危機対策において、エネルギー貧困となる低所得者層の課題を解決しながらゼロカーボン都市の実現に取組むことが重要だと考えますが、いかがか伺います。また、エネルギー貧困への暮らしの支援など自治体の役割についてどのようにお考えか伺います。
2点目は、エアコン設置支援についてです。
札幌市消防局の2025年、熱中症による救急搬送概要では、5月から8月までの4カ月で582人が搬送されており、発生場所は住居が326人と一番多い状況です。高齢者は、加齢に伴って体温調節機能が低下し、熱さを感じにくくなるほか、喉の渇きにも鈍感になる傾向があります。また、乳幼児や病気、障害を持つ家族を抱えている世帯でも、エアコンでの室内の温度調節が欠かせません。
北海道の夏の暑さは、今後も強まる傾向となっており、エアコン設置が当り前となってきています。市場調査によるエアコン設置率では、北海道は59%、札幌市は54.2%と全国の88%からも低い実態です。市民の生活は、物価高騰に追いつかない賃金や年金により、先が見えない苦しさがあると推測できます。国の助成制度は、リフォームとセットであり、また、札幌市のエネルギー源転換補助金制度は、灯油暖房、灯油給湯ボイラーをやめて寒冷地エアコンなどに切り替えることが条件となっており、気軽に利用できません。エアコンの設置・購入に直接支援する施策が必要です。
他都市が実施している事業を参考に、札幌市においても「命を守る」ことを最優先に、エアコン設置、購入費への助成事業の実施を検討すべきと考えますが、お考えを伺います。
3点目は、クーリングシェルターの充実についてです。
札幌市は、市民が夏の暑さを避けて無料で利用できる施設として民間施設や市有施設合わせて198施設の指定暑熱避難施設「クーリングシェルター」を設置しています。
クーリングシェルターの利用には、炎天下に移動することを考えると自宅から近い身近な場所に設置することが望ましく、市民からも「自宅に近いところにあってほしい」「座れる場所が欲しい」などの要望が届いています。
これまでの「クーリングシェルター」の利用状況や場所の提供に協力いただいた施設や利用者の意見を把握して、事業の検証し、今後のクーリングシェルターの充実につなげるべきと考えますがいかがか伺います。
4点目は、教育施設と体育館のエアコン設置についてです。
教育施設のエアコン設置状況は、2027年度末までに完了を目指す計画で、約6千台を設置する計画です。
しかし、事業者の人手不足や学校ごとに異なる電気設備の改修の必要性などから時間がかかっており、今年度設置されなかった学校の保護者からは「来年の夏には設置されるだろうか」と不安の声が届いています。そこで伺いますが、すべての学校へのエアコン設置の見通しについて伺います。
また、エアコンが設置されていない学校では、引き続き、移動式エアコンが使われますが、排熱が出るため、「冷やしても冷房の効果が少ない」などの声も届いているところです。
移動式エアコンの排熱を室外に出していく対応や台数を増やす等、工夫が必要と考えますが、どのように対処されるお考えなのか伺います。
さらに、国が学校施設の避難所機能強化などの観点から、学校体育館への空調設備整備臨時特例交付金事業を2024年(令6年)から2033年(令15年)を対象期間として、算定割合2分の1の内容で実施しています。札幌市においてもこの交付事業を利用して、避難所となる学校の体育館への空調(冷房)設備の設置計画を検討すべきですが、お考えを伺います。
次は、OTC類似薬の保険適用除外についてです。
質問の第1は、市民生活への影響についてです。
日本の医療は、長年にわたり診療報酬制度という公定価格制度によって支えられてきました。しかし、コロナ禍の最中から多くの医療機関が経営悪化を訴えてきたにも関わらず診療報酬を抑制したことにより、昨今の物価高騰や人件費の上昇に対応できず医療現場は深刻な経営危機に直面しています。
こうしたことから、日本病院会をはじめとする6つの主要医療団体が連名で、政府に対して補正予算による緊急支援を求める要望書を提出しています。また、全国知事会や、札幌市も加盟する政令指定都市市長会も、医療機関への早急な支援を求めており、医療現場における経営危機は、地域における住民への医療提供体制に影響を及ぼす課題であると考えられます。
このような中で、「経済財政運営と改革の基本方針2025」いわゆる骨太の方針2025において、政府は、国の医療費削減を口実に、OTC類似薬の保険適用を除外しようとしています。
OTC類似薬とは、医療用医薬品のうち、同じ有効成分や類似した効果を持つ市販薬が存在するものを指し、対象となるのは、解熱鎮痛薬、湿布薬、抗アレルギー薬などです。保険適用から除外されれば、今後はドラッグストア等で、全額自己負担で購入せざるをえなく、市民生活の大きな負担となります。また、現在でも受診せず自己判断による市販薬の使用により副作用や病状が悪化してから、医療機関を受診するケースがあることなどから医療現場は強い懸念を示しています。
またOTC類似薬保険外しで、難病医療助成からも外される可能性があることから、難病患者の皆さんが、重大な政策変更であり、命と健康が守れないと保険適用の存続を求めています。
そこで質問ですが、市長は、OTC類似薬の保険適用除外が及ぼす市民生活の影響についてどのようにお考えなのか伺います。
質問の第2は、子ども医療費助成制度への影響についてです。
札幌市は今年度から、子ども医療費助成制度を高校3年生まで拡充し、子育て世帯からは「症状が軽いうちに病院へ行けるようになったので、重症化を防げていると思う」「子育て支援につながる制度が嬉しい」と喜ばれています。
しかし、処方箋が対象外となれば、OTC類似薬の購入費用は子ども医療費助成制度の対象外となり、子育て世帯の負担増になります。
札幌市が子育て支援として積み上げてきた子ども医療費助成制度の効果が損なわれることについて、市長はどのように受け止めているのか伺います。
最後に、障がい福祉サービス報酬改定による影響と対策についてです。
2005 年に介護保険を原型に制度化された現行の障害福祉制度は、支援の量と質を支える財政基盤となる事業報酬を見直す「報酬改定」が3年に1度行なわれ、2024年度に 6 度目の改定が行なわれました。
報酬改定では、支援の基準や要件、基本報酬単位が見直されてきました。とりわけ、基本報酬の見直しは事業所運営の基本財源であり、支援の内容・水準に影響を及ぼすことになります。
質問の第1は、地域で暮らす障がい者を支える障がい福祉事業所への影響と対策についてです。
障がいがあっても、地域で自分らしく生きていけるように生活や住まいの場、そして働く場を提供し、支援をすることが障がい福祉事業所です。
きょうされんが実施した2024年度報酬改定の影響調査結果によると、障がい当事者の生活の場である生活介護事業所や住まいの場であるGH事業所の7割以上で基本報酬が減収となっております。
定員4,5人の小規模なGH事業所ほど減収が多く、その影響を受けて小規模GH事業所数は2021年からの5年間毎年減り続けています。
また、障がい者の仕事の場である就労支援事業の報酬改定では、工賃収入が多いほど報酬単価が高くなる成果主義が一層強化されたため、職員の残業が増えています。
一方で、一日の生活リズムを整え他者との関わりを通じて地域社会で安定して過ごすことを目的に働く障がい者は、高い工賃を得ることができないため、受け入れる事業所は、手厚い支援が必要であるにもかかわらず、報酬費が低く抑えられます。光熱費や物価高騰が続く中、事業者の努力だけでは、事業継続は限界です。
報酬改定により札幌市内の障がい福祉事業所にどのような影響があるか実態を把握し、事業報酬のあり方を改めるよう国に求めるべきだと思いますがいかがか。また、減収などにより、事業縮小や閉所となる懸念がある障がい福祉事業所に対して、財政的支援など本市としての対策が求められると思いますが、いかがか伺います。
質問の第2は、障がい福祉事業の人材確保・定着への取組についてです。
障がい福祉支援の現場においては、「求人を出しても、応募が1人もない」、「職員が足りなくて、十分な支援ができない」など、深刻な「職員不足」の状態が続いており、障がい者の高齢化や福祉ニーズの複合化・複雑化している現状において、福祉人材確保・定着支援のさらなる強化が求められます。
1点目は、事業報酬の加算による処遇改善策についてです。
福祉分野における人手不足は、賃金が全産業平均より低すぎることに起因します。
国は、障がい福祉人材の確保・定着のための処遇改善策として、事業所の基本報酬に加えて要件を満たすことを条件とした加算の創設、拡充などを行ってきており、昨年度は、すべての福祉職員の賃金を引き上げることを目的とした処遇改善加算に対し加算率の引上げと事業所内で柔軟な職種間配分ができるようになりました。
しかし、障がい福祉事業所において要件を満たしていても加算未取得の事業所が一定数あり、小規模ほど多くなっています。
事業所規模などの違いによって事業所間で福祉職員の賃金格差があってはなりません。
札幌市として、加算未取得の障がい福祉事業所の実態を把握し、その事業所で働く福祉職員の賃上げ等の処遇改善ができるよう支援が必要と思いますがいかがか、伺います。
条件による加算ではなく、人件費として全ての福祉事業所が取得できる基本報酬の引き上げを本市として国に対し求めるべきだと思いますが、いかがか伺います。
2点目は、障がい福祉事業所への事務職員の配置についてです。
障がい福祉事業所では、事務職員の配置が事業報酬に含まれていません。
福祉専門職員は、経理などの作業も担っているため、本来の福祉支援業務に専念できません。また、業務時間外、休日出勤をして事務作業を行っている実態があります。中には、福祉職員の人件費や事業運営費を削り、事務職員を配置している事業所もありますが、それが、福祉職員の賃金の引上げを困難にしている要因の一つとなっています。
障がい福祉サービス分野における人員配置として事務職員配置を加えることは、障がい福祉サービスの質の向上につながります。
札幌市として、市内の障がい福祉事業所のこのような実態を把握し、改善策をとる必要があると思いますが、いかがか伺います。
以上で、私の質問のすべてを終わります。ご清聴、ありがとうございました。
秋元市長 答弁
全体で7項目にわたりご質問いただきました。私からは大きな1項目目、私の政治姿勢についてのご質問に対しての2項目、それから大きな3項目目のまちづくりに関しての2項目についてお答えをさせていただきます。その余のご質問に対しましては、担当の天野副市長、山本副市長、加藤副市長、教育長からお答えをさせていただきます。
まず、私の政治姿勢についての1項目目、多文化共生社会と排外主義についてお答えをいたします。1点目の外国人に関する事実の歪曲とその宣伝・拡散行為についてでありますが、最近の外国人をめぐる批判的な情報の拡散は、国民の物価高騰などによる生活への不安や閉塞感が背景にあり、異なる文化や価値観を受け入れることへの理解が十分ではないことによるものと思慮しております。今後、札幌市においても、外国籍市民の増加が予想される状況において、互いの文化や風習の違いを理解し合い、誰もが住みやすい地域社会を実現することが重要であろうと考えております。このため、今後も円滑なコミュニケーションを確保するための日本語習得支援や国際交流員による地域への出前講座、多文化共生の文イベントでの交流などを通じ、引き続き相互理解を深めてまいりたいと考えております。
2点目の様々な民族の存在の否定と多文化共生社会についてであります。特定の人種や民族に対する差別的行為はまことに恥ずべきものであり、また、アイヌ政策推進法でもアイヌであることを理由とした差別は禁止しているものと認識をしております。一方で、札幌駅前通り地下広場などの公の施設の使用制限については、地方自治法上、また判例上も極めて原則的とするべきとされているところであります。今後につきましては、当事者の声に加え、有識者や法の専門家の意見等も丁寧に伺いながら、今後の対応を検討し、もって共生社会の実現に努めていくとともに、様々な事業や啓発活動などを通じて、アイヌ民族に対する理解促進に努めてまいりたいと考えております。
次に、私の政治姿勢についての2項目目、泊原発とGX特区についてお答えをいたします。1点目の泊原発3号機の再稼働への動きについてであります。原子力発電につきましては、何よりも安全性の確保が大前提であり、安全性や必要性については、国が責任を持って丁寧な説明を行い、国民の理解と信頼を得ていくことが重要であろうと考えております。泊原発3号機の再稼働につきましては、原子力規制委員会による科学的・技術的な見地からの厳格な安全審査を経て判断されたものと承知をしております。北海道知事も再稼働については安全性の確保が大前提と、私と同様の考えを持った上で、総合的に判断されるものと認識をしており、今後も情報収集に努めてまいります。
次に、2点目のGX特区によるESG債の使途についてであります。札幌証券取引所が創設をいたしました「北海道ESGプロボンドマーケット」は、所定の評価機関によるESG評価取得等の要件を満たした社債等のみを取り扱うESG債に特化した市場であり、国内外からのESG投資の促進を目的としたものであります。本市場に上場される社債等については、証券取引所が定める要件に基づいて審査されていると認識をしており、民間企業が発行する社債等の資金使途などについて、市長の立場で見解を申し上げるものではないと考えております。また、原子力発電につきましては、省エネの推進や再生可能エネルギーの拡大を図っていく中で、可能な限りその依存度を低減していくことが重要だと認識をしております。
次に、大きな3項目目のまちづくりに関してお答えをいたします。まず、その1項目目の開発優先のまちづくりについてであります。1点目の新MICE施設整備方針基本方針についてでありますが、取得予定地は新MICE施設の整備に最適な立地であり、まちづくりで活用すべき重要な土地であると認識をしていることから、基本計画の検討に先立ち、札幌市が確保すべきものと判断をしたところであります。用地取得価格につきましては、今後も地価が変動する可能性を踏まえて、売買契約の締結を予定している令和10年度に、改めて不動産鑑定を行い、その評価額に基づいて適正に算定する考えであります。なお、用地取得の前には、施設整備事業について議会にお諮りをする考えであります。また、パブリックコメントは、基本計画の策定段階において市民意見を反映する大切な機会であると認識をしており、今後も様々な広報活動を通じて事業の意義や効果などを分かりやすく発信をし、市民の理解を得ながら着実に事業を進めてまいります。
次に、まちづくりについての開発優先のまちづくりについての2点目、都心アクセス道路の地元負担と需要や効果についてお答えをいたします。一般国道5号創成川通「都心アクセス道路整備事業」は、令和3年度に北海道開発局において事業化されたものでありますが、昨今の資機材や労務単価の上昇による影響は、同事業に対しても一定程度あるものと見込まれるところであります。このため、札幌市の関連工事においては、効率的な執行に努めるとともに、北海道開発局に対しても、より一層のコスト縮減や効率的な事業執行に努めていただけるよう、引き続き働きかけてまいります。また、本事業の需要及び整備効果につきましては、令和2年度と令和5年度に北海道開発局が実施をいたしました事業評価のプロセスの中で、札幌市もその内容を確認するとともに、その後の第三者委員会による審議を経て、妥当との結論が得られておりますことから、適切に事業が進められているものと認識をしております。
次に、まちづくりについてのご質問のうちの2項目目、住民のためのまちづくりについてお答えをいたします。まず1点目の市民置き去りのまちづくりについてということでありますが、札幌市では、政令指定都市移行後に重点的に整備をした公共施設の更新需要が近年本格化しており、将来の人口減少を見据えると、全ての公共施設を維持し続けることは難しいものと考えております。このため、市民生活に欠かすことのできない必要な機能は維持しつつも、利用者数の減少や民間事業者によるサービス提供が可能になるなどの環境変化も考慮し、今後も行政が担い続けるべき施設を選択をし、維持・更新を進めているところであります。こうした取り組みを進めるにあたりましては、例えば市立保育所の廃止の方向性については、利用者に対し説明会を開催の上、そのご理解をいただいたものであります。また、しらぎく荘につきましても、老朽化について入居者にご理解をいただいた上で、全ての方が退所された時点で廃止を決定したところであります。このように、これまでも施設の廃止縮小においては、市民への説明に意を用いてきたところでもあり、今後とも市民の理解を得る努力を進めてまいります。
次に2点目の優先すべき事業についてでありますが、ご指摘の例えば病院や下水道、さらには道路の修繕やバリアフリー化ももちろんでありますが、その他の施設インフラにつきましても、市民の命や暮らしにおいて、いずれも重要な施設だと考えているところであります。市の施設について何を優先していくかに関しては、限りある財源を有効活用するためにも大変重要なことであると認識をしております。例えば、予算編成の中でこれまで的確に検討してきたところでありますが、今後とも適時適切に計画的な施設の更新を進めてまいりたい、このように考えております。私からは以上です。
天野副市長 答弁
私からは大きな2項目目、市民の暮らしと市民負担増についての2項目目、自治体の役割と来年度から実施予定の市民負担増にかかる計画見直しについての3点目、市営住宅の管理戸数の見直しと公平性、自治体の役割分担について、大きな5項目目、気候危機と暑さ対策についての1項目目、札幌市気候変動対策行動計画について、2項目目、猛暑に対応した市民生活への支援についての3点目、クーリングシェルターの充実についてお答えをさせていただきます。
まずは、大きな2項目目の市民の暮らしと市民負担増についての2項目目、自治体の役割と来年度から実施予定の市民負担増にかかる計画の見直しについての3点目の市営住宅の管理戸数の見直しと公平性、自治体の公的の公的役割についてでございますが、今後の人口減少や民間賃貸住宅における空き家の状況等を踏まえ、市営住宅の管理戸数は抑制していくことを基本としております。市営住宅の家賃は、応能応益家賃制度に基づきまして、これまでも住宅の利便性に応じて必要な増額と減額を行ってきております。今後も公営住宅法に則り、低額所得者に住宅を供給する役割を果たしてまいります。
次に、大きな5項目目、気候危機と暑さ対策についての1項目目、札幌市気候変動対策行動計画についてでございます。市内の温室効果ガスの排出状況としましては、最新のデータである2022年の排出量は1,022万トンであり、計画の基準年である2016年比では172万トン、2030年目標の55%対し、約14%の削減となっております。現計画における課題につきましては、再エネの導入拡大による削減が比較的順調に進んでいる一方で、省エネや移動の脱炭素化については遅れが見られる状況が挙げられます。また、原計画の見直しにつきましては、現在、札幌市環境審議会でこれらの課題を共有し、議論を重ねているところでございます。委員の意見を踏まえながら、改訂作業を進めてまいりたいと考えております。
次に2項目目、猛暑に対応した市民生活への支援についての3点目のクーリングシェルターの充実についてでございます。令和6年の改正気候変動適応法の施行を受け、昨年から民間施設にもご協力いただきながら、クーリングシェルターの指定を進めているところでございます。今年度も全施設を対象に、利用者の声を含めたアンケートを行う予定であり、寄せられた意見を参考に、来年度、来年度の実施に生かしてまいりたいと考えております。私からは以上でございます。
山本副市長 答弁
私からは大きな2項目目、市民の暮らしと市民負担増についての2項目目、自治体の役割と来年度から実施予定の市民負担増にかかる計画の見直しについての1点目、敬老パス制度の継続と検証、2点目、火葬料金有料化による市民負担等、4点目、市民負担増の認識と見直しの市長の決断について、そして、大きな5項目目、気候危機と暑さ対策についての2項目目になります猛暑に対応した市民生活への支援について、この1点目、エネルギー貧困への認識と札幌市の役割、2点目のエアコン設置支援について、そして大きな6項目目、OTC類似薬の保険適用除外について、そして大きな7項目目、障害福祉サービス報酬改定による影響と対策について、についてお答えを申し上げます。
まず、大きな2項目目、市民の暮らしと市民負担増についての2項目目、自治体の役割と来年度から実施予定の市民負担増にかかる計画の見直しについての1点目、敬老パス制度の継続と検証についてであります。新制度への移行は、約1年半の間、市民や議会と議論を重ね、パブリックコメントの結果も踏まえたものであり、制度を利用する世代と支える世代の双方から一定の理解が得られたものと認識しており、令和8年度から着実に進めてまいります。
2点目の火葬料金有料化による市民負担等についてであります。新たな料金制度は、市民意見を反映させるとともに、議会においてしっかりとご審議をいただいた上で、利用者に相応の負担を求めるものであります。来年度からの実施に向けて、引き続き丁寧に周知をしてまいります。
次に、4点目の市民負担増の認識と見直しの市長の決断についてであります。昨今の物価高騰の中、これらの制度の見直しは市民に一定程度のご負担をお願いするものではありますが、持続可能な施設管理や行政サービスの安定的な提供のためには、社会的・経済的状況の変化に対応した見直しを適時適切に行う必要があると考えており、今後も丁寧な説明に努めてまいります。
次に大きな5項目目、気候危機と暑さ対策についての2項目目、猛暑に対応した市民生活への支援についてであります。その1点目のエネルギー貧困への認識と札幌市の役割についてであります。ゼロカーボン都市の実現に向けた取り組みは、市民の暮らしへの影響や様々な社会課題を考慮しながら進めていく必要があると認識をしております。札幌市としては、これまで住民税非課税世帯への給付金の支給などに取り組むとともに、国に対してエネルギー価格の負担軽減策の実施を要請してきたところであります。今後も国の経済対策等の動向を注視し、必要な支援を行ってまいります。
2点目のエアコン設置支援についてであります。近年、札幌においても夏の猛暑が続いており、市民の健康への影響が懸念されるところであります。そのため、札幌市では様々な熱中症対策を進めているところであり、引き続き効果的な対策について検討してまいります。
次に大きな6項目目、OTC類似薬の保険適用除外についてであります。まず、市民生活への影響についてであります。OTC類似薬の保険適用除外につきましては、国における持続可能な社会保障制度のための改革の一環として議論されているところであります。見直しにあたりましては、必要な受診の確保や慢性疾患を抱えている方などの負担に配慮しながら検討が行われていると承知をしており、国におきまして適切な制度設計がなされるよう、議論の推移を注視してまいります。
次に、子ども医療費助成制度への影響についてであります。札幌市の医療費助成制度は、公的医療保険の自己負担分を助成するものでありまして、今後も適切に運用してまいります。
次に、大きな7項目目、障害福祉サービス報酬改定による影響と対策についてであります。まず1項目目、地域で暮らす障がい者を支える障がい福祉事業所への影響と対策についてであります。令和6年度の報酬改定では、実態を踏まえて障がい程度とサービス提供時間に応じた基本報酬になった一方で、重度障がいのある方の受け入れや支援内容に応じた加算が充実するなど、全国的に課題となっている事業所の支援の質の向上に資する改定であったと認識をしております。令和6年度の市内事業所の状況は、減収となった事業所も多いことでありますが、加算を含めますと、生活介護の約6割、グループホームの約5割が増収となっており、今後も引き続き実態把握に努めてまいります。
2項目目、障がい福祉事業の人材確保定着への取組についてであります。まず1点目の事業報酬の加算による処遇改善策についてであります。処遇改善加算の取得に必要な事務手続きに負担を感じている事業所も多いと考え、令和2年度から社会保険労務士等を派遣し支援するなど、市内全事業所の約9割が処遇改善加算を取得しております。処遇改善加算は、障がい福祉人材の確保や定着につながり、サービスの向上にも資することから、引き続き未取得の事業所に対し、運営指導などを通じて加算の取得を働きかけてまいります。
2点目の障がい福祉事業所への事務職員の配置についてであります。障害福祉サービスの報酬は、報酬には事務経費も含まれておりますが、札幌市としては事務負担の軽減がサービス向上につながると考えまして、今年度から請求事務を管理するソフトウェアなどICT導入に対する補助を開始したところであります。今後も事業所の声を聞きながら必要な支援を行い、質の高い障がい福祉サービスの提供につなげてまいります。私からは以上です。
加藤副市長 答弁
私からは、大きな項目の2点目、市民の暮らしと市民負担増についての1点目、物価高騰における札幌市経済への影響について及び大きな項目の4つ目、中小企業支援についてについてお答えいたします。
まず、大きな項目の2つ目、市民の暮らしと市民負担増についての1点目、物価高騰における札幌市経済への影響についてでございます。長引く物価高騰は、札幌市経済を支える企業の活動に様々な影響を与えるものと認識してございます。札幌市企業経営動向調査から、仕入れ価格の上昇などが企業経営に直接的な影響を与えていることを確認しているほか、国の調査から、「可処分所得の減少が販売量の落ち込みにつながっている」といった影響を指摘する声も把握しているところでございます。
次に、大きな項目の4つ目、中小企業支援についてでございます。中小企業が賃上げを行うためには、経営基盤を強化していくことが重要であることから、札幌市においては生産性向上や販路拡大支援に加えまして、低利な融資制度の運用や札幌中小企業支援センターにおける経営相談など、個々の事業所の状況に寄り添った支援を実施しているところでございます。今後もこのような支援を継続していくほか、国に対しまして、中小企業が賃上げに取り組みやすい環境整備や資金繰りを含めた経営基盤強化につきまして、引き続き要望していくなど、経営の安定に向けた支援を取り組んでまいりたいと考えてございます。以上でございます。
山根教育長 答弁
私からは、大きな5項目目の気候危機と暑さ対策についての2項目目、猛暑に対応した市民生活への支援についてのうち、4点目の教育施設と体育館のエアコン設置についてお答えをいたします。
市立幼稚園・学校の普通教室等のエアコンにつきましては、可能な限り整備の前倒しを図りながら、令和8年夏までに全体の約7割、令和9年夏には新改築等で整備を行う学校を除き、全ての学校で使用を開始する見通しであります。エアコン設置が完了するまでの間につきましては、学校現場における運用面でもきめ細やかな対応を行い、児童生徒の安全に配慮してまいります。体育館のエアコン整備につきましては、設備条件や整備コストなど様々な課題がありますことから、まずはそれらの調査を進めているところであります。私からは以上であります。
田中議員 再質問
2点、再質問させていただきます。1点目は、泊原発とGX特区についてです。答弁で、原子力発電については、省エネの推進、再生可能エネルギーの拡大で可能な限り依存度の低減を図っていく旨の答弁だったと思います。この再エネで電力需要を十分に賄っていけるようになるまでには、長い期間がかかっていくということは周知の事実であります。この再エネに移行していく間の代替エネルギーとして、原子力発電で賄うということにならないか、そのことをまず確認させてください。
2点目、中小企業支援についてです。札幌市が低金利の融資、経営相談してきていることは承知しております。質問でも述べたように、給付あるいは助成金による賃上げ支援、金利を据え置いた上での返済期限の延長などの支援、こちらが切実に求められております。国の制度設計、待たないで、札幌市として支援実施に踏み出してほしいことを求めておりますが、改めてお伺いいたします。
秋元市長 答弁
再質問いただきました。私からは泊原発とGX特区に関連してお答えをさせていただきます。原子力発電につきましては、将来的に原発に頼らない、そういう社会を実現をしていくことが望ましいというふうに考えております。そういう意味で、たとえ過渡的なエネルギーとして再稼働が選択される場合であっても、安全性の確保、これが大前提であるというふうに考えてございます。私から以上です。
加藤副市長 答弁
私からは中小企業支援につきましてお答えをいたします。札幌市の融資制度につきましては、資金の返済期限の猶予や借り換えにつきましても適宜認めるなど、事業者に寄り添った支援を実施しているところでございます。また、中小企業が賃上げや価格転嫁ができる環境整備につきましては、引き続き国に要望してまいりたいと考えてございます。以上でございます。