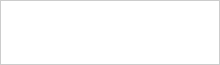私は、日本共産党を代表し、ただいま議題となっております議案7件中、議案第1号「令和6年度札幌市各会計歳入歳出決算認定の件」、議案第6号「令和6年度札幌市水道事業会計剰余金処分及び決算認定の件」、並びに議案第7号「令和6年度札幌市下水道事業会計決算認定の件」に反対、残余の議案には賛成の立場から討論を行います。
私は、日本共産党を代表し、ただいま議題となっております議案7件中、議案第1号「令和6年度札幌市各会計歳入歳出決算認定の件」、議案第6号「令和6年度札幌市水道事業会計剰余金処分及び決算認定の件」、並びに議案第7号「令和6年度札幌市下水道事業会計決算認定の件」に反対、残余の議案には賛成の立場から討論を行います。
2024年度一般会計決算は、歳入約1兆2,401億8,800万円にたいし、歳出約1兆2,303億円と、最終予算額にたいする歳出の執行率は92.5%となりました。
歳入から歳出を差し引いた形式収支は98億8,800万円、翌年度繰越財源を差し引いた決算剰余金は42億1,800万円です。このうち財政調整基金に22億円を積立てた結果、基金の年度末残高は283億円となりました。
我が党はこれまでも、財政調整基金は市民の大切な財産であり、必要に応じて適切に取り崩して市民生活や福祉に資する事業に活用すべきと求めてきました。現在の基金残高は、アクションプランで「維持すべき水準」とされる100億円を大きく上回っており、厳しさを増す市民生活の実態を踏まえれば、基金をより積極的に活用する余地があったと指摘いたします。
2024年度は、住民票などの証明書等発行手数料や市有施設の利用料の値上げ、市民の火葬料の有料化など市民負担が次々決められました。物価高騰で厳しい生活になっている市民の負担を軽減することを優先し、実施は見直すべきです。
議案第1号に反対する理由の第1は、不要不急の大型開発計画や、市民の充分な合意が図られていない事業が含まれているからです。
北海道新幹線推進関係費、都心まちづくり推進費のうち札幌駅交流拠点まちづくり推進費、新幹線札幌駅東改札口整備関連費、大通・創世交流拠点まちづくり推進費、また都心アクセス道路事業を進めるための創成川通機能強化検討調査費と直轄事業負担金、さらに民間再開発促進費などの約100億円は、いずれも北海道新幹線の2030年開業に向けた整備をめざしたものですが、2024年時点で札幌延伸工事の遅れは明らかです。
北海道新幹線延伸工事や「2030年開業ありき」で進められてきたこれら事業については、市の負担金や補助金の見通しを明らかにするためにも、いったん立ち止まり、事業評価を行い、その規模や工期を見直すことも含めて検討に入るべきでした。また、掘削残土の処理をめぐっても、いまだ住民合意は得られていません。こうした状況を踏まえれば、切実に求められていた市独自の物価高騰対策や、バス路線の維持、市営住宅の整備など遅れている生活インフラ整備を最優先に位置付ける判断こそ必要であったと申し上げます。
なお、議案第6号、議案第7号についても、都心アクセス道路整備に伴う上下水道管路の移設に93億円が使われたため反対です。
理由の第2は、マイナンバー制度関連費として8億6,687万円が使われたためです。
マイナンバーカードの取得は任意であるはずです。しかし、自治体に対しその普及推進が強く求められ、保険証との一体化などカード利用の対象を更に拡大しようとしています。個人情報が集積されるほど、漏洩やプライバシー侵害の危険が高まること、国による国民監視を強める仕組みとなっていることから、マイナンバー制度は廃止すべきです。
理由の第3は、高齢者健康寿命延伸費2億8116万円は、来年度からの敬老優待乗車証・敬老パスの事業縮小を前提とした健康アプリのシステム開発事業費であるためです。
2024年9月に、健康アプリと同時に提案された変更案に対しても市民の反対の声は大きく、敬老パス制度縮小に反対する請願、陳情が相次ぎ、署名は6万筆を超えました。 これらのことから市民は敬老パスの縮小は望んでいないことは明らかであり、来年度に予定されている事業縮小は、ただちに停止すべきです。
理由の第4は、学校新増改築費の中に、学校規模適正化、いわゆる学校統廃合に関する費用として761万円使われているからです。
この費用は、学校統廃合を検討する「学校配置検討委員会」の協議内容を周知するための経費です。
しかし、学校統廃合は、児童生徒の通学条件の悪化や学校の大規模化による教育環境の変化など様々な懸念があります。そのため、児童生徒をはじめ、保護者や地域住民などの合意形成が不可欠であり、検討のあり方を見直すべきです。
理由の第5は、「札幌市職員定数条例の一部を改正する条例」により、本市の職員63名が削減されたからです。
理由の第6は、国民健康保険、後期高齢者医療において、高い保険料がさらに引き上げられたためです。
理由の第7は、札幌市営住宅の管理戸数を抑制するという方針のもと、借り上げ市営住宅の4団地、182戸の用途を廃止し、削減したため反対するものです。
決算特別委員会でも取り上げましたが、市営住宅の結露やカビによる修繕の入居者負担を見直し、改善を検討すべきこと、また、未修繕の空き住戸2389戸を速やかに修繕すべきことを合わせて求めます。
次に代表質問並びに、決算特別委員会で取り上げた諸課題について、局別に申し述べます。
代表質問で、泊原発3号機の再稼働への動きとGX特区によるESG債の使途について質問しました。
市長は、「GX特区」となってからも、これまで同様、省エネ推進や再生可能エネルギーを拡大することで、原発への依存度を低減すると説明されてきました。
北海道電力が発行した社債の使途について、「見解を申し上げるものではない」と答弁されましたが、再稼働につながるものであり、原発依存度低減にはならないことを申し上げます。
はじめに総務局です。
会計年度任用職員制度についてです。
本市の多様な部局において会計年度任用職員が採用され、行政の仕事を担っています。本市は、各部署へのヒアリング等を通じて実態を確認し、来年度から任用限度3年を原則としつつ、3年到達後も同一部署での任用を可能とする手続きを進めているとの答弁でした。
国は、「公募3年要件」を撤廃しており、本市においても3年有期雇用の見直しを行うよう求めます。
デジタル戦略推進局です。
自衛官募集事務に係る対象者情報の提供についてです。
満18歳・22歳の住民の個人情報を提供する、自衛隊への名簿提供について「法令上の義務ではないものと認識している」との答弁がありました。満18歳になっていない未成年者の情報も提供されており、ただちにやめるべきと強く求めます。
まちづくり政策局です。
代替交通についてです。
昨年度から本年4月までの市内路線バスの減廃便は1002便にものぼりますが、札幌市地域公共交通計画にある「代替交通」の運行は、わずか2路線に留まります。本市が定めた「代替交通」の導入基準を柔軟に見直し、拡充を図るべきです。
都心部の路上公共交通の円滑な移動環境についてです。
本市の「総合交通計画」では、都心部の交通円滑化が示されていますが、自動車流入抑制策の効果は十分に確認できていません。再開発の進展により車両流入の増加も懸念されます。
駐車場や観光バスの利用実態を把握し、効果的な対策で都心部の路上公共交通の円滑化を図られるよう求めます。
市民文化局です。
博物館整備推進についてです。
札幌の独自性や国際的な学術研究の成果を展示することは、市民の学びや関心、愛着を深めるものであり、札幌の魅力を発信できる観光拠点としても重要です。改めて市民と議論を重ね、計画を前に進めていただくよう求めます。
スポーツ局です。
藻岩山スキー場についてです。
昨年度、新たな運営体制として、北海道スクエアが選定され、札幌市とりんゆう観光との3者で協定が締結されました。今後も市民に親しまれ愛される藻岩山市民スキー場となるよう求めます。
保健福祉局です。
障がい者施策についてです。
精神障がい者保健福祉手帳と自立支援受給者証については、他の障がい者手帳同様に、更新案内を早急に送付し、確実に更新できるようにすべきです。
敬老パスの再交付についてです。
身体的な理由などで自主的に敬老パスを返還した市民が、状況が改善された後に再交付を求めても認められません。 高齢者の外出を促し、社会参加を支援することで、健康寿命の延伸や老後の生活を充実させるという敬老パスの目的に沿うよう要綱や交付規則などを変更し、再交付について柔軟に対応するよう求めます。
子ども医療費助成について質問しました。
所得制限とあわせ初診料の窓口一部負担もなくし、子ども医療費の完全無償化を早期に実現するよう求めます。
ひとり親家庭の親の通院医療費助成は、非課税世帯が対象です。入院と同じように、課税世帯にも早急に助成を広げるべきです。
子ども未来局です。
民間学童保育所への支援について質問しました。
本市独自の取組である保育料減免や家賃補助制度について、社会情勢の変化に応じた見直しを行うよう求めました。放課後児童健全育成事業の一翼を担う民間学童保育所に対し、助成の引上げや保護者負担の軽減を求めます。
社会的養護のもとで育つ子どもの「意見表明」についてです。
札幌市は、第三者であるアドボケイトを養成し、児童養護施設で子どもの意見表明を支援しています。
今後は、里親家庭などにも対象を広げることや、現場の課題に応じた改善を進めることで、子どもの権利がより実効性をもって保障されるよう取り組むことを求めます。
次に、経済観光局です。
中小企業等の製造業省エネカーボンニュートラル促進支援事業についてです。
昨年度は、1社が実施し、年間の二酸化炭素削減目標を約10tとしていたところ、実際には約18t削減されました。効果が確認されている事業であることから、来年度予算の増額を検討し、取組む企業数を拡大されるよう求めます。
新MICE施設整備についてです。
国際会議や学会などの誘致を目的とするこの事業は、整備計画の検討やパブリックコメントの実施前に、土地取得の予約契約を金額を示さないまま市議会に諮るという前例のない手法がとられました。このような事実上の白紙委任を求める進め方に、市民の理解や合意が得られていません。
また、総事業費は当初の280億円から592億円と2倍以上に増大しています。新設ではなく、札幌コンベンションセンターなど既存の実績ある施設や民間施設の活用を工夫することで十分に対応が可能です。
したがって、本事業については、いったん立ち止まるべきです。
札幌農業の地産地消と鳥獣被害対策についてです。
「第3次さっぽろ都市農業ビジョン」作成にあたっては、地産地消推進のために、産地表示としての「さっぽろとれたてっこ」の取り組み促進のための議論を進め、札幌の農産物を市民が身近に感じられるビジョンとなるよう求めます。
今後も体制強化をはかり、農業者の鳥獣被害を少なくしていただくよう求めます。
環境局です。
家庭ごみ有料化から16年が経過し、2008年に約42万トンあった廃棄ごみ量は昨年度約26万トンまで減少しました。市民の減量・リサイクル意識は定着しており、現行の手数料、いわゆる指定ごみ袋の手数料を維持する必要性は薄れています。市民負担軽減のため手数料の減額を検討するべきです。
次に、建設局です。
厚別山本公園のアクションスポーツエリアについてです。4月に厚別山本公園にオープンした、スケートボードなどが楽しめるエリアは、午後4時30分までしか利用できません。時間を延ばして欲しいとの声をお聞きしました。「利用者アンケートを実施して協議したい」とのことですので、早急に延長するよう申し上げます。
下水道河川局では、下水道の点検・調査の安全確保についてお聞きしました。
埼玉県八潮市の道路陥没事故を受け、現在、実施されている「全国特別重点調査」においては、他都市では硫化水素中毒が原因とされる死亡事故が発生しています。委員会で本市が答弁されたように委託事業者任せにせず、発注者としての責任を持って安全確保に取組むよう求めます。
次に都市局です。
木造住宅耐震化の促進についてです。
木造住宅耐震化補助事業は、工事に至るものが年10軒ほどに留まっており、費用面がその一因となっています。
補助金を事業者が直接受け取る「代理受領制度」は、住宅所有者の負担感を軽減できるため、耐震改修の促進に有効です。本市においても本制度の導入を検討するよう求めます。
また、来年度に策定される「第4次札幌市耐震改修促進計画」においては、本市の地震被害想定に合わせた対応として、補助事業の対象を2000年5月までの新耐震基準まで広げ、住宅の耐震化を進めるよう求めます。
最後に教育委員会です。
不登校児童への支援について質疑しました。
本市の不登校児童・生徒は2023年度5715人で、2019年度からの5年間で2倍程度と増加傾向が続いています。市内10区に設置されている学校外での「教育支援センター」には現在約400名が利用しているとのことでした。学習や運動等の活動を通した支援は、不登校となった児童生徒が、周りの大人との信頼関係を築く大事な活動です。
教育支援センターの活動内容を知らずに悩んでいる保護者等がまだいることも考えられることから、利用の促進を図ること、また学校や保護者との連携を強化するなど一人ひとりの子どもに向きあったきめ細かい対応に、引き続き努力されるよう求めます。
以上で、私の討論を終わります。